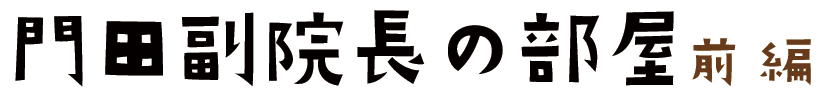
倉敷中央病院副院長 門田 一繁 先生
日本内科学会認定医、
総合内科専門医、指導医
日本循環器学会専門医
日本心血管インターベンション治療学会専門医
出身地: 愛媛県
好きな食べ物: 和菓子(つぶあん派)
趣味: 家庭菜園


的確な判断が求められる仕事
門田先生、よろしくお願いします!
ご出身はどちらですか?
門田副院長:
愛媛です。
海の近くやって、
開けた感じの田舎です(笑)。
お医者さんになられたきっかけは?
門田副院長:
両親の勧めがきっかけで。
うちは農家をやってて、
「農家を継ぐのか、あるいは
他の職業なら医者がいいんじゃない?」
ちゅうふうな感じで。
それがきっかけで!?
門田副院長:
きっかけは(笑)。
でもやっぱり、
その職業を選んだからには
全うせんといかんやん。
医者という職業を選んだんだから、
そこで求められることを頑張らないとなあ、
いう想いがあるよね。
では、お医者さんになろう!と思われて、
その後、専門として
循環器内科の道を選ばれたのは?
門田副院長:
そこは結構な想いがあるね・ ・ ・。
循環器内科は、内科系の中でも
自分の判断ひとつで、すぐ結果につながる。
心筋梗塞にしても、
急性心不全にしても、
いかに早く診断をつけて、
早い段階でいろんなことを評価して、
すぐに治療につなげて・ ・ ・。
適切なタイミングで治療していかないと
いけない。
ちょっと大げさかもしれないけど、
自分の判断が「救命」につながっていく、
そこにやりがいを感じたね。
なるほど。
ところで先生、
お部屋に飾ってあるこちらの絵は?

接吻 | グスタフ・クリムト
門田副院長:
これはねえ・ ・ ・。
一緒に働かせていただいた故・光藤和明先生の。
(※元倉敷中央病院副院長・心臓病センター長)
元々飾ってあったのを、
そのままにしてるねんけど。
別の絵に変えてもいいかなという思いも
あるんだけど、ただ・・・。
ただ・・・なんとなく光藤先生を感じるような。
門田副院長:
うんうん。
そういう思いがあるんで、
むしろ別の絵をもうひとつ
違うところに置こうかなと思って。
絵を変えるのは何か・・・
何か良くないと思ってるんですよ(笑)。
別の絵をかけられるとすれば何をここに?
門田副院長:
僕が考えてんのは、
ベルナール・ビュッフェって画家知ってる?
・・・すみません、不勉強で。
先生、美術もお詳しいんですか?
門田副院長:
そこまでではないけど(笑)
新たな治療法とともに歩んだ医療の道
門田先生はPCIの著書を出されていますよね。
この技術が始まったのは、 ちょうど先生が
お医者さんになられた頃からでしょうか?
PCI:経皮的冠動脈インターベンション 血管の詰まり、狭くなった部分を広げて、血液のスムーズな流れを取り戻す治療の一種。
詳しくは倉敷中央病院循環器内科のページをご覧ください。
だいたいその頃ですね。
そういう意味では、
心臓のカテーテル(血管に通す細い管)治療、
PCIとともに生きてきたようなもんよね。
光藤先生がその分野のパイオニアだったから、
振り返ってみると、
その最先端の技術に関わりながら
やってこられた、ていうのが
興味深く、勉強になったよね。

患者さんにとって、
手術するよりも負担が軽いですよね。
門田副院長:
最初はバイパス手術
(※胸を開いて、詰まった冠動脈の先に
迂回路(バイパス)をつくる手術)
しかなかったのが、
だんだん発展してきていますよね。
それは、ひとつには
高齢者とか、負担の軽い治療を望まれる人が
どんどん増えてきているのもあるよね。
これまで最先端の心臓病治療に
携わって来られたのですね。
ところで、
お仕事で大事にされていることは
何でしょうか?
門田副院長:
こだわることが大事
なんじゃないかなと思っていて。
一例一例、
治療がスムーズにいく場合もあれば、
そうでないケースもある。
でも、そのままにはせずに、
何か些細な変化があったときに
原因を突き止めて次の段階の治療に活かす。
そういうところにこだわるのが、やっぱり
大事なんじゃないかなと思いますよね。
一人ひとり、
丁寧な診療が大事ということですね。
一人の患者さんに多面的にかかわる医療
くらちゅうが目指す
「地域医療エコシステム」について、
先生が循環器内科で診療されている中で、
どのように捉えていらっしゃいますか?
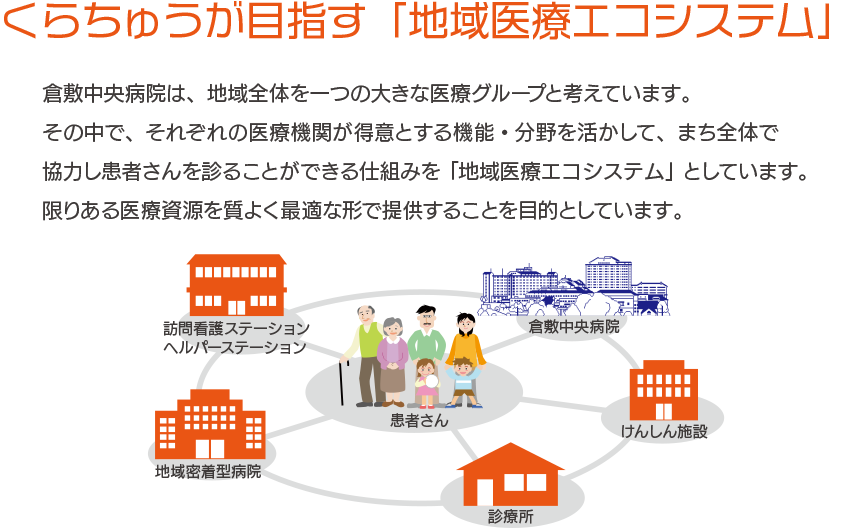
門田副院長:
うん。
くらちゅうは
重症患者を診る急性期病院だから、
紹介患者さんを診たりとか、
救急医療に力を注ぐとか、
その役割だけ全うしていたらいいのかな、
そんなふうに思うじゃない?
でもね、
くらちゅうでの治療後、かかりつけ医へ
ただ紹介状を送って、
「はい、お願いします」
というだけの一方的な紹介は、患者さんに
とっていい形にならないこともある。
これまでの地域連携をみていくと、
それが分かってきたね。
くらちゅうとかかりつけ医、
どちらも同じ目標で、
患者さんの時間軸も考えながら、
しっかり診ていくことが大事。
かかりつけ医へ紹介して
終わりではない・ ・ ・?
門田副院長:
つまり、
くらちゅうへ受診してもらわないにしても、
数ヶ月後とか1年後の時点で、
かかりつけの先生と同じ目標を共有できる
ような仕組みをつくっていかないと。
治療目標のすり合わせ、ということですか?
門田副院長:
そうだね。
紹介状を出すだけの一方通行では、
問題があるのかなぁ、とも思います。
それと、
同じ循環器内科の病気でも、例えば、
もともとくらちゅうで心筋梗塞を診てたけど、
次にくらちゅうに入院したときには
心不全とか不整脈とか発症していることもあって。
いろんな疾患全般を合わせて診る、ゆうのも
必要じゃないかなあと思うよね。
高齢化が進んできて、
ひとつの疾患だけでなく、
複数の疾患を持たれている方が多い。
それをいろんな先生が診られている場合も
あるので、そこの連携をどう取るか、
ということでしょうか。
門田副院長:
うん。
循環器の疾患の中でもいろいろあるし、
さらに言えば、
病院の先生は臓器別に専門が分かれていて、
循環器内科、消化器内科、外科・・・と、
複数の先生が診ているとなかなか
患者さんの全身状態が把握されないこともある。
全体を総合して診ていくのは、
病院の先生では難しい部分があって、
そこはかかりつけの先生が全体的に診ていく、
という形が大事なんじゃないかな、と思うね。
専門の先生とかかりつけ医との連携ですね。
かかりつけ医が日ごろ患者の全身状態を診る
けど、悪化したり専門治療が必要になって
くると、くらちゅうへまた紹介する。
これはまさしく
「地域医療エコシステム」ですね。
門田副院長:
うん。
進化する連携
門田副院長:
それともうひとつ、
循環器内科の連携について言うと
循環器内科は専門医が地域にもおられて、
昔はあまり十分な連携でなかったんだけど、
くらちゅうで心臓病の治療をした後に
そのまま全ての患者さんの心臓リハビリを
くらちゅうだけで担うことは、
医療資源も限られており、難しい。
そこで、地域の病院が自然発生的に
心臓リハビリをし始めたので、
地域の中でうまく役割分担が
できるようになったね。
これまで地域の医療機関と連携を
していたことが、
心臓リハビリでも活かされたんですね!
門田副院長:
さらに言えば、
医師同士だけでなく、
看護師や薬剤師など多職種を交えての
連携もやっていくべきかなあ、
と思いますよね。
お薬のことでも、
薬剤師さんに任せきりではなく、
もう少し我々も関わらんといけないなと。
病院・職種・診療科、
それぞれの輪がたくさんあるけど、
それをつないでいくことが
今後重要なんじゃないかな。

今は同じ職種とか、診療科とか、
まずは近いところで連携を
取っているところですけど、
実際に患者さんに関わるところとなると、
もっと広いということですね。
門田副院長:
これも「地域医療エコシステム」の1つのあり方だと思います。
さらに連携が深まりますね!
今回はここまで。
次回も引き続き門田副院長に
お話を伺っていきます。
皆さんお楽しみに!
