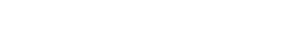大原美術館レポート
大原美術館訪問 初期臨床研修医が感じたこと
2025年度採用者の気づき・学び
大原孫三郎の精神に触れて
倉敷中央病院に入職するにあたって、オリエンテーションとして大原美術館の見学をさせていただいた。事前にしていただいた講義では大原孫三郎の「社会のために役立つことは何か」という考えと、それに基づいた児島虎次郎に対する西洋作品の収集の支援、そして大原美術館の設立までを詳しく知ることができ、それが東西の芸術の交流の起点となって日本の芸術家に西洋の芸術に触れる機会を与えることで「社会のために役立つ」活動となっていたことが印象深かった。
美術館の中では実際に虎次郎が集めた西洋の作品や虎次郎自身の作品、その後に集められた作品などを目にすることができ、大変貴重な経験ができたと感じている。今後は私も社会に役立つことは何かを考えながら研修に励みたいと思う。
社会にとって意義のあることとは何か
正直に述べると、私は大原孫三郎や大原美術館の創立の経緯について全く知識がない状態で見学日を迎えたため、楽しめるかどうか不安だった。ところが実際には、美術館見学前の講義で、天領地である倉敷での大原家の台頭、孫三郎の実業家や社会事業家としての顔、児島虎次郎との出逢いについて学ぶことができ、大原美術館のオーバービューについて知った上で作品を鑑賞することができ、レポートを書くということを忘れて没頭できた。
講義の中では、孫三郎が「社会にとって意義のあることとは何か」を追究する姿勢について繰り返し言及されており、その姿勢の結晶として倉敷中央病院を含む現在の倉敷、ひいては中国地方の経済社会が存在することを実感した。また、そのような姿勢が孫三郎の子の總一郎などの子孫にも受け継がれ、常にその時代の新進気鋭の作家の作品を取り入れる姿勢にも医師としてあるべき姿を重ねた。つまり、自分が研修医として何ができるか、何をすべきかを常に考えるとともに、将来のキャリアを見据えて生涯学習を続けるべきなのだと感じた。新社会人としてこの気持ちを維持して2年間の研修に臨みたい。
倉敷で本物に触れる
大原美術館の見学では最初に、倉敷の歴史、そして大原孫三郎をはじめとする大原一族が倉敷で行ってきた事業についての説明を受けました。一番印象に残っていることは、大原孫三郎の「非営利かつ公益性の高い事業をする」という信念です。その信念のもとに、孤児院の設立の支援を行ったり、児島虎次郎を支援することによって西洋の美術作品の収集・展示を行ったりしたとお聞きしました。その信念は病院の設立にも影響を与えており、患者さんのために当時では珍しかったエレベーターを作ったり、温室を作ったりしたと知り、そのような環境で働けることを嬉しく思いました。
説明を受けた後に、実際に大原美術館を見学してみると、西洋と日本、中国など様々な文化圏の美術作品、そして、数百年前から現代に至る時代を超えた作品が並んでおり、ジャンルに縛られない自由な視点で芸術を楽しめました。個人的に一番印象に残った作品は、モネの「睡蓮」です。モネの作品はパリの美術館などで展示されていると聞いていたので、パリから遠く離れた倉敷の土地で見ることが出来たことにとても感動したとともに、これこそが大原孫三郎、そして児島虎次郎たちの努力のもとに実現された、民衆のための事業であると感じました。
新しい土地で芸術に触れるとともに、この新鮮な気持ちを忘れずに新生活を頑張ろうとさらに気の引き締まる思いになりました。末筆になりますが、説明・案内をしてくださったスタッフの皆様、ありがとうございました。
プロフェッショナリズムと奉仕の精神
“受胎告知”の前に立つ。今は亡き祖父に手を引かれてこの絵を見た、温かな思い出が胸に広がる。あの時も美しい絵だと思った。しかし、今日は違って見えた。肌の色も、影の色も、ただの白や黒ではない。複雑な色の混ざり合いが、脳に鮮明な像を残し、詳細を省くタッチが、人物の機敏を雄大に語り出す。素人目にも、傑作と思える絵だった。そして今、この絵が、児島虎次郎が確かな知識と感性に基づいて選び、人々の為にはるばる持ち帰った物だと、私は知っている。そして、そこには、大原孫三郎の奉仕の精神に基づく、献身的な援助があった。私はもう、目の前の絵画を単なる絵として見ることはできない。私は手を引かれる幼子ではいられないのだ。
背筋の伸びる思いで、会館を出ると、咲き始めた桜が目に入った。暖かな風に揺れる桜の花も、蕾から花開く時は、今の私の胸の様に、痛みを感じていたのだろうと、私は思う。鑑賞を通して、大原孫三郎と児島虎次郎が、プロフェッショナリズムと奉仕の精神で人々に尽くしてきた事を深く学び、感動した。私も医師として、人々に貢献し、地域の一員として生きてゆきたい。
倉敷中央病院のルーツと病院らしさを感じさせない工夫
大原美術館の見学に行きました。
大原孫三郎の「私がこの資産を与えられたのは、私の為ではない。世界の為である。」という精神に触れながら、倉敷中央病院のルーツについて知ることができました。
絵画を見ている間は、「なぜこのテーマで描いたのだろう」「何を伝えたいのだろう」と自由に作品に対して想像を巡らす時間がありました。気づくと日常生活から一旦離れリフレッシュされた感覚がありました。
院内に絵画が展示されていたり温室が設置されていたり建物全体のレンガ調のデザインなど、「病院らしさを感じさせない工夫」は色々な思いを抱えている患者さんの心の休息になっているのかなと思いました。
また、今後医療者として一緒に励んでいく同期と交流しながら、美術館見学できたのはとても良い思い出です。これからも同期との楽しい思い出も増やしながら、一日一日の研修を大切にしていきたいと思います。