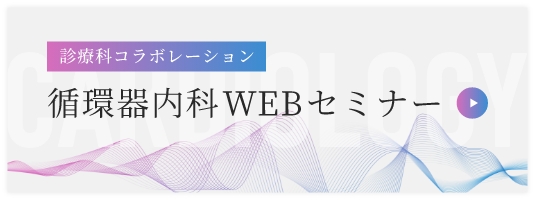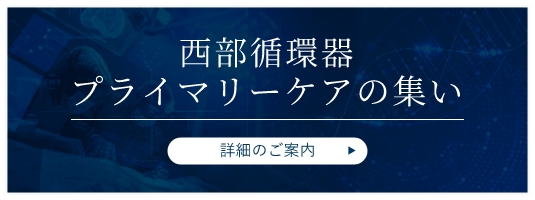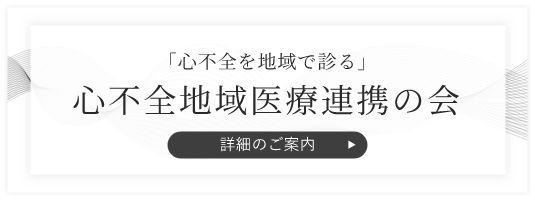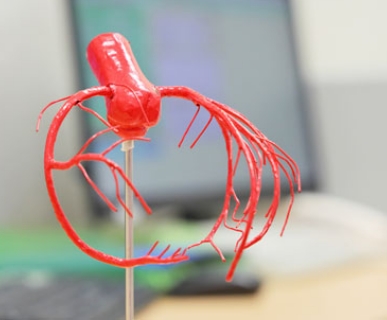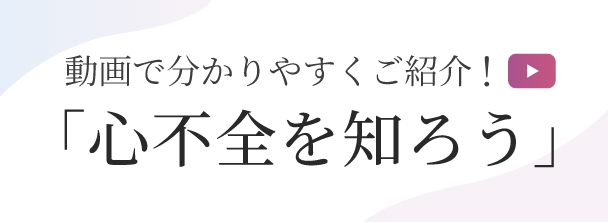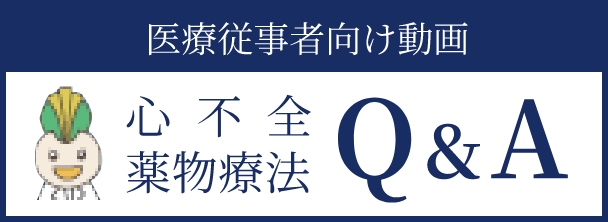イベント・お知らせ

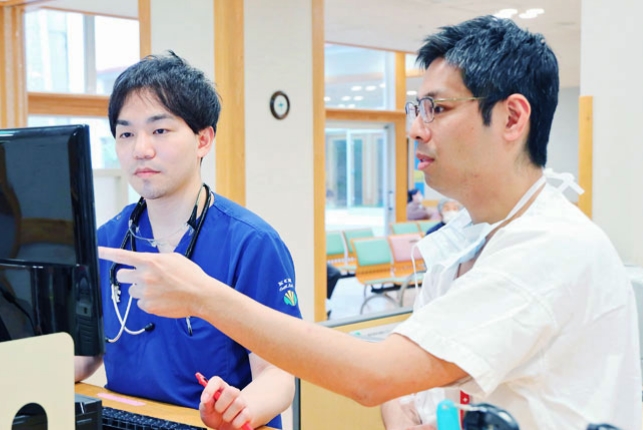
ABOUT
「最良質の地域医療」
を提供する
現代の基幹病院として、倉敷という地域で、
世界標準あるいはそれを超える最良質の医療を提供すること、
すなわち「最良質の地域医療」が30年来の我々の目標であり、
これからも変わることはありません。
循環器疾患について
TEAM
地域チーム医療への取組み
当科では地位全体としての循環器医療の貢献を目的として、
お互いの治療・管理の実際と概念の理解を深めるため、
定期的な検討会や情報交換の場を設けています。
そうした基盤を持った地域チーム医療の中では、
患者さんにもより安心できる医療を提供できると考えています。
当科の取組み
RECRUIT
循環器内科医を志す方へ
私たちは「世界標準の医療を倉敷に」の理念のもとに、
最先端の医療に取り組みながら、多くの人材が長い歴史を紡いできました。
決して安易な道ではありませんが、興味を抱いていただけたならば、
いちど倉敷に見学にお越しください。

当日受診希望の方
岡山県内の一般電話・公衆電話
0120-336-117
岡山県外・携帯電話・PHS
086-422-5065
【倉敷中央病院コールセンター】
月~金曜日 9:00 ~ 11:00
(土・休日を除く)
紹介状をお持ちで
受診日が決まっていない方
一般電話・公衆電話
086-422-9020
【倉敷中央病院地域医療連携室】
月~金曜日 13:00 ~ 16:30
心臓の病気は、一刻を争う重度な病気の場合もあります。
症状がある場合は、迷わず救急外来にお越し下さい。