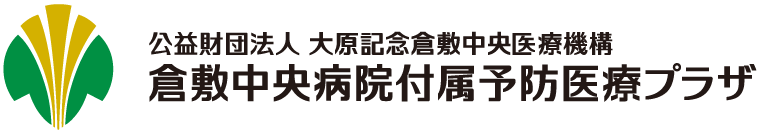検査項目の説明
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 問診 | 問診 | 提出していただいた問診票をもとに、看護師が、既往歴や家族歴、自覚症状やその他生活の背景などの様子をうかがい、正しい検査を行うための参考にします。健診結果を生活習慣の改善に生かすためのフォローアップにも役立てることができます。 |
| 計測 | 身体計測 |
身長や体重を測定し、肥満度をチェックします。肥満度が高いと動脈硬化や高血圧、糖尿病などの生活習慣病にかかる可能性が高くなります。 (注意)体脂肪率の測定には、インピーダンス法を使用しています。ペースメーカーを挿入中の方は測定できませんので必ずお申し出下さい。 |
| 腹囲 | おへその周りを測定し、内臓脂肪の蓄積の程度を調べています。男性85㎝以上、女性90㎝以上あると、内臓脂肪面積が100平方㎝相当と言われ、生活習慣病のリスクが高まります。 | |
| 視力 | 5m先のものがどれだけ見えるかを測定しています。肉眼で見たときの裸眼視力、もしくはメガネやコンタクトレンズを使用したときの矯正視力を測定します。1.0以上が「基準範囲」、0.7~0.9が「要注意」、0.6以下が「異常」とされています。 | |
| 眼底 |
動脈や網膜の状態を調べる検査です。眼底は人体で唯一、体表面から動脈を観察できる部分で、動脈硬化や眼底出血などが分かります。 Scheie分類 S:動脈硬化性 H:高血圧性 |
|
| 眼圧 |
眼圧とは眼内液(房水)の圧力をいいます。眼球に空気を吹き付け、簡易的に測定します。眼圧が高くなると、視神経が圧迫され視野が狭くなる緑内障などの可能性が高まります。 (注意) コンタクトレンズを使用されている場合は測定できませんので、一時的にはずしていただきます。 |
|
| 聴力 | 低音域(1000HZ)、高音域(4000HZ)の聴力を調べています。数値(dB)が大きくなるほど聴力低下の度合いが強いことを表します。 | |
| 呼吸器 | 胸部X線 | X線(放射線)をからだに照射し、うつし出された画像をチェックして、肺や心臓の状態を調べます。 |
| 胸部CT | 従来の胸部X腺では発見できなかった、小さい早期の肺がんや、心臓や横隔膜に重なって発見困難であった肺がんが検出でき、肺がんの検出率が向上します。 | |
| 呼吸機能検査 | 大きく息を吸ったり吐いたりして、呼吸障害の有無や程度を調べる検査です。 喫煙者では慢性閉塞性肺疾患(COPD)の有無を見ることができます。 |
|
| 喀痰細胞診 | 痰を顕微鏡で見ることで、肺や気管支に病変がないかを調べます。気管支にできる肺がんは、CT検査でも発見しにくいことがあります。喀痰細胞診検査はこの気管支にできた癌の発見にすぐれています。 専用の容器に3日分の痰を採取していただきます。 |
|
| 循環器 | 血圧 | 血圧が高い状態が続くと心臓病や脳卒中などの危険性が高くなります。基準値は129/84mmHg以下で、これを超えると要注意です。 |
| 脈拍 | 脈拍の正常値は、一般成人で1分間に60~100回を正常値の範囲としています。 | |
| 心電図 | 心臓が血液を送り出すときに発する電気を読み取り、波形として記録します。心拍数や電流の流れ具合に異常がないか心筋、冠動脈などの状態を調べます。 | |
| BNP | 心臓に負担がかかると分泌されるホルモンの検査です。高値の場合は心機能が低下している可能性があります。 | |
| 消化器 | 上部消化管X線 |
レントゲンで胃や十二指腸、食道などに異常がないかを調べる検査です。胃の粘膜を観察するために、発泡剤とバリウムを服用してから撮影します。食べ物の残りなどがあると適切な像が得られませんので、絶食などの注意を守っていただく必要があります。 (注意) 治療中のご病気の状態や、ご高齢の方、便通の状態によっては検査を延期または中止させていただき、胃カメラへの変更をおすすめすることがあります。便秘の強い方は、前もって下剤などで便通を整えておかれることをおすすめします。 |
| 上部消化管内視鏡 (胃カメラ) |
予約制(電話でお申し込み下さい) 口から内視鏡(先端にレンズのついた管)を入れて胃の状態を観察する検査です。メリットは胃の内部の色調なども確認できることなどがあります。 |
|
| 超音波 | 上腹部超音波 | 超音波で腹部臓器を検査します。お腹にゼリーを塗って検査しますが痛みなどはありません。肝臓・胆のう・腎臓・脾臓・膵臓などの異常を知ることができます。 膵臓は奥深い場所にあるため、観察しづらい場合があります。 |
| 頚動脈超音波 | 頸動脈の状態(血管壁の厚み、血管内プラークの有無や大きさなど)を調べ、動脈硬化の早期発見に役立ちます。頚動脈は動脈硬化の好発部位であることから、全身の動脈硬化の進行をおおむね把握することができます。 | |
| 肝機能 | 総蛋白 | 数値が低い場合は栄養障害、ネフローゼ症候群、がんなど、高い場合は多発性骨髄腫、慢性炎症、脱水などが疑われます。 |
| アルブミン | 血液中に含まれるたんぱく質のうちでもっとも多く、肝臓で合成されます。栄養障害や肝臓や腎臓の障害により値が低くなります。 | |
| A/G比 | 蛋白質であるアルブミンをグロブリンで割った比で、栄養状態の指標になります。 | |
| 総ビリルビン 直接ビリルビン |
黄疸の指標です。肝機能障害や胆道障害などがあると、ビリルビンが血液中に増加します。 | |
| AST(GOT) |
心臓・筋肉・肝臓に多く存在する酵素です。肝臓病の有無について調べます。 |
|
| ALT(GPT) | 肝臓に多く存在する酵素です。肝臓が炎症を起こすと上昇します。急性肝炎または慢性肝炎が悪化した時には急上昇します。 | |
| LDH | 糖が体内でエネルギーに変わる時に働く酵素です。臓器に異常があると高値を示します。特に急性肝炎や肝臓がん、あるいは心筋梗塞のときに著しく増加します。 | |
| ALP | 肝臓・胆道・骨・腎臓などに多く含まれる酵素です。これらの臓器に異常があると高くなります。 | |
| コリンエステラーゼ | 肝臓で作られる酵素です。肝障害が進むと低下しますが、脂肪肝では上昇します。 | |
| γ-GTP | 肝臓の解毒作用に関係する酵素です。アルコールの飲みすぎや薬剤が原因で肝臓に異常が起こると上昇します。閉塞性黄疸でも上昇します。 | |
| HBs抗原 | B型肝炎ウイルスの検査です。 陽性の場合は、現在B型肝炎ウイルスが体内にいることを意味します。 |
|
| HCV抗体 |
C型肝炎ウイルスの検査です。 ※過去にC型肝炎にかかり治った場合も陽性となります。 |
|
| 尿ウロビリノーゲン | 胆汁内に含まれるビリルビンが腸内細菌によって分解されてできる物質です。肝臓や胆道系に異常があると増加します。 | |
| 脂質 | 総コレステロール | 増えすぎると動脈硬化の原因になり、心臓病や脳卒中を起こしやすくなります。 |
| HDLコレステロール | 善玉コレステロールと呼ばれ、血液中の悪玉コレステロールを回収し動脈硬化を予防する働きがあります。運動不足・喫煙などで値が低くなり、動脈硬化の危険性が高まります。 | |
| LDLコレステロール | 悪玉コレステロールと呼ばれ、血管壁に蓄積すると動脈硬化を進行させ、脳卒中や心臓病などを起こす危険性を高めます。 | |
| 中性脂肪 | 糖質がエネルギーとして脂肪に変化したものです。肥満、飲酒、過食などで増加します。数値が高いと動脈硬化を進行させます。低いと、低βリポたんぱく血症、低栄養などが疑われます。 | |
| 電解質 | Na・K・Cl | 体内の水分調節や神経の伝達、筋肉の収縮などの役割を果たす電解質の濃度を測定し、バランスの状態を見ます。 |
| 大腸 | 便潜血 |
便に血液が混じっているかどうか調べる大腸がんの検査です。便潜血が陽性だった場合、3人に1人は大腸ポリープが、40~50人に1人は大腸がんが見つかっています。陽性の場合は精密検査を受けましょう。 |
| 大腸内視鏡 |
予約制(電話でお申し込み下さい) 肛門から内視鏡を挿入し、大腸(直腸から盲腸)の粘膜に生じた病変(炎症、潰瘍、がん、憩室など)を直接観察する検査です。病変の形状や大きさだけでなく、表面の色や模様、出血の様子なども詳しく観察できます。 |
|
| 腎機能 | 尿蛋白 | 血液中に含まれるタンパク質が尿中に出てきたもので、陽性の場合は腎臓、尿管などの障害が疑われます。 激しい運動後やストレス、糖尿病などでも陽性になる場合があります。 |
| 尿潜血 | 腎臓や尿管、膀胱など、尿の通り道に異常があると尿に血液が混じることがあります。 | |
| PH | 尿のPHを調べることで尿の酸性・アルカリ性を知ることができます。 | |
| 尿沈渣 | 肉眼では見えない様々な細胞や細菌が含まれていないか顕微鏡で調べます。 | |
| 尿比重 | 尿の濃縮・希釈の状態をみます。脱水傾向や糖尿病であれば高値、水分摂取過剰や尿崩症では低値となります。 | |
| 尿素窒素 | たんぱく質が分解されるときにできる老廃物の一種です。尿中に排泄されますが腎機能に異常があると血液中に増えるため、その量を測定します。腎機能が正常に機能しているかを知るための指標になります。 | |
| クレアチニン | アミノ酸の一種であるクレアチニンが代謝されたあとの老廃物のことで、血液中のクレアチニンの濃度から腎機能の障害の有無を調べます。腎臓の機能が低下すると上昇します。 | |
| eGFR | 腎臓にどれくらい老廃物を尿へ排泄する能力があるかを示しており、この値が低いほど腎臓の働きが悪いということになります。 | |
| 尿酸 | たんぱく質の一種であるプリン体から分解された老廃物の血液中の量を測定します。高い値が続くと、足の親指の付け根やひざの関節に炎症をおこしたり、激しい痛みを伴ったりする痛風の原因になります。 | |
| 血液一般 | 赤血球数 | 全身の組織に酵素を運ぶ赤血球の数を調べます。赤血球数を測ることにより、貧血や多血症の有無がわかります。 |
| 白血球数 | 体内に侵入してくるウイルスや細菌を退治するしくみを免疫といい、その中心的役割を果たす白血球の量を調べます。細菌感染による炎症を起こしているかどうかの判定に役立ちます。 | |
| ヘモグロビン | 貧血の検査です。ヘモグロビンが不足すると、酸素の運搬が十分に行われないため、貧血状態になります。 | |
| ヘマトクリット | 血液に含まれている赤血球の割合です。貧血などを調べます。 | |
| 血小板 | 出血した部分に粘着して出血を止める役割を果たす血小板の数を調べます。 | |
| MCV | 赤血球の容積を表します。(平均赤血球容積) | |
| MCH | 赤血球の中に含まれるヘモグロビン量の平均値を表します。(平均赤血球血色素量) | |
| MCHC | 赤血球容積に対するヘモグロビン量の割合を示します。(平均赤血球血色素濃度) | |
| 白血球分類 | 白血球の各種(好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球類)がどのような割合で血液中にあるかを調べ、どの種類が増減しているかで病気の診断を行います。 | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | 血糖を下げるインスリンの不足やその働きが悪くなると高くなります。 |
| 尿糖定性 | 尿中の糖の有無を調べます。血糖値が上昇した時に陽性になりますが、腎性糖尿では、血糖値が上昇していなくても陽性になることがあります。 | |
| ヘモグロビンA1c | 過去1~2ヶ月の血糖の平均値を反映します。糖尿病で高くなります。 | |
| 75g糖負荷テスト | 75gのブドウ糖水溶液を飲み、血糖値がどのように推移するかをみます。空腹時血糖だけでは診断できないような、境界型の糖尿病がないか調べます。 | |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | 膵臓が正常に機能しているかを検査します。 |
| 腫瘍マーカー | CEA AFP PSA(男性) CA125(女性) CA19-9 |
悪性腫瘍の可能性を調べる検査です。良性疾患でも高値となることがあります。一種の補助的診断方法ですので決定的なものではなく、他の検査とあわせると診断に役立ちます。 CEA・・・・ 大腸がん、肺がん、腫瘍全般の診断指標 |
| その他 | CRP | 細菌やウイルスの感染、けが、病気などによって体に炎症が起きると肝臓でつくられ、血中に増えるたんぱく質です。細菌感染症・膠原病などの炎症疾患などで上昇します。 |
| 体組成検査 |
体脂肪や筋肉量、体の水分量や基礎代謝量など、見かけや体重だけではわからない体の中身について調べます。 (注意)ペースメーカーを使用している方や妊娠中の方は検査できません。 |