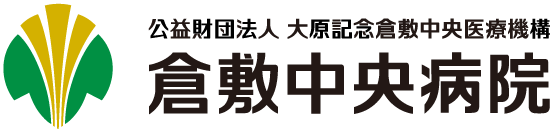医療と介護のつどい in 倉中 各回のポイント
 つどいでは毎回、グループワークを行っています。当院と介護を支える皆さんとでよりよい連携を築いてゆくための課題や改善に向けた取り組みが、ここで生まれています。
つどいでは毎回、グループワークを行っています。当院と介護を支える皆さんとでよりよい連携を築いてゆくための課題や改善に向けた取り組みが、ここで生まれています。
2016年、第1回開催で見えた課題
初回ということもあり、普段はケアマネジャーと直接交流する機会のない当院スタッフの参加も多かったため、まずは、それぞれが感じている問題点や課題をざっくばらんに出し合いました。これらの課題について、今後回を重ねて解決に向けて検討していくことにしました。
- 相談窓⼝がわかりづらい(窓⼝が明確でない、どこに相談したらよいかわからない)
- MSWと連携しづらい(介⼊していないケースの相談は可能か、どういう動きをしているか)
- 情報共有がしづらい(連携シートが活⽤できていない、⼿段がわかりづらい、共通⽤語でない)
- ⽂書のやりとりが円滑にいかない(窓⼝がわかりづらい、時間がかかる)
- 医師、看護師やリハビリスタッフと連携したいが、どういう⼿段がよいかわからない
外来患者について連携を深めるために
それぞれの立場で取りくめることをお互いに語り合ったことで、連携の必要性への理解が深まりました。一方、外来との連携が深まるためには具体的な対応策の検討が必要ということも見えてきました。
●ケアマネジャーと倉中、お互いに取り組めそうなこと
(ケアマネジャー)
- お薬手帳に名刺を入れて、ケアマネジャーがついていることを知らせる
- ケアマネジャーが適宜受診に同行して誰が担当か倉中スタッフへわかるようにする
- 情報の伝え方を工夫する(簡潔な文書、FAX、ファイルの運用)
- 医師宛だけでなく外来看護師宛に情報を発信していく
(倉中)
- 退院前カンファの際に、ケアマネジャーに診療科・相談窓口が分かるように伝える
- 入院から外来へのサマリによる情報共有をしっかり行う
- 気になる患者についての外来でのカンファレンス実施
- 窓口の明確化
●グループワークで見えた課題
- 個人情報のため、電話で誰が・どこまで伝えられるか
- 正しい情報をスムーズに確認して共有できる方法の検討
ケアマネジャーとの連携改善に向けて
講義では、当院の病棟看護師の⼊退院⽀援にかかわる動きを紹介しながら、ケアマネジャーとの連携の場⾯や悩む点について共有しました。その上で、3つのグループワークを通して、下記について取り組むこととしました。
- 患者さんに医療保険や介護保険の保険証と⼀緒にケアマネジャーの名刺を保管してもらうように働きかける。
当院でも担当ケアマネジャーの事業所・⽒名・連絡先をしっかり確認する。 - ケアマネジャーの連携シートは情報共有のツールとして活⽤する。
- ⼊院患者に関するケアマネジャーの来院窓⼝は、1-65(⼊退院⽀援センター)に⼀本化。
情報共有が有意義に⾏える体制を作る。
●グループワークで見えた課題
- 個人情報のため、電話で誰が・どこまで伝えられるか
- 正しい情報をスムーズに確認して共有できる方法の検討
事前の情報共有と相談窓口明確化でスムーズな連携へ!
倉中・ケアマネジャーともに満足度が高く、院内スタッフのうち9割は持ち帰って部署内で共有できるという結果でした。ケアマネジャーについても、個人情報の取り扱いについて「理解が深まった」が97%、窓口一本化で「連携がしやすくなった」が97%、「倉中と情報共有しやすくなった」が89%という結果となりました。
●課題①個人情報の取り扱い
倉中・ケアマネジャーともに今後は以下について注意して取り組むこととなりました。
- 患者本人や家族に状況を確認し同意を得た上で情報のやり取りをすること
- 「なぜその情報が必要なのか」を伝える/確認すること
- 倉中では患者照合のため氏名・生年月日の2点確認が必要なこと
- 入院時に患者・家族からケアマネジャーへの情報提供に同意が得られない場合にはお伝えできないこと
- 職種の限界や把握している情報が異なるため、問い合わせにその場で伝えられる情報には限りがあり、欲しい情報を事前に伝えてもらうことで円滑なやり取りができること
●課題②相談窓口の明確化
- 入院時窓口一本化により、ケアマネジャー・病棟看護師相互に連携がスムーズになったという意見が大半でしたが、手間が増えること、対応する側のマンパワーを心配される声、事前アポイントの負担について課題があがりました。
→今後は、原則として初回来院時(連携シート持参時)のみ1-65を経由し案内。2度目以降の訪問については病棟あるいはMSWへ事前アポイントの上で直接病棟へ来院いただくこととした。直接病棟を訪ねることが困難な場合には初回同様の対応とする。 - 外来の相談窓口が決まるとアプローチがしやすいという声が多い一方、スタッフによって対応が異なるという指摘もありました。
→ケアマネジャーから直接は外来看護師に連絡しづらいため、今後は、外来での相談はMSWにまず連絡をいただき、そこから院内多職種へ繋ぐことで対応する。スタッフ教育は引き続き必要。
課題③円滑な情報共有
残る課題としては、退院後の連携であり、特に薬の問題が大きいこと。ケアマネジャーとの顔の見える関係を作り、さらに円滑に連携を図ることができるようにしていくことが必要という意見があがりました。
見えてきた新たな課題
- 薬の管理(情報不足、管理の問題、一包化など)
- 入院から外来への引継ぎ(職種間)
- 通院しかない患者について情報収集のツールがない
- 入院前生活情報での同意の確認と周知 連携シートの活用
- ケアマネジャーには様々な職歴の方がいるため、共通用語でのコミュニケーションが必要
倉中、地域の視点でお薬の連携課題を抽出!
倉中でも院外処方は可能であり、一包化が必要な場合などは患者さんにお申し出いただきたいことや、患者さんがうまく伝えられない場合には あらかじめMSWを通じて外来看護師へ事情を説明すればサポートが得られることなどを共有した上で、円滑に進めるうえでの問題点がグループワークで見えてきました。
●倉中側の課題
- 院内に院外処方の場合の依頼ルートがない。
- 薬のことで院外から問い合わせがあった場合の窓口がない。
- 院内の各診療科から処方が多数出る場合など、院内薬剤師にて重複や減薬についてチェックできないか。
- 地域の薬局が訪問指導などどこまで対応できるのか、薬局の情報がない。
- 残薬チェックや薬袋変更など、取り組みはあっても周知されていない。
- 頓服がto do処方で増えていく。
●地域の課題
- 保険薬局では、需要の少ない薬は受注発注となる。薬価が高額な場合のリスクがある。
- FAXで依頼が入り翌日受け取りになるなど、時間に余裕をもって依頼があれば準備ができるが、院外処方の需要が増えるとどこまで対応できるか不安がある。
- かかりつけ薬局を持つことで、薬の一元管理ができるというメリットはあるが、減薬するにも各HPのどこに照会をすればよいのかわからず対応に困る。
薬に関する相談窓口が明確に
講演では、当院薬剤部のポリファーマシーへの取り組みや診療科への介入事例が示され、かかりつけ医・かかりつけ薬剤師にポリファーマシーの薬剤調整が認識されていないという問題点を共有しました。また、薬で困った際には
薬剤部調剤室(直通422-8908)
または
医療福祉相談室(直通422-5063)※8:30~17:15
へ連絡すれば適切な部署へつなぐことを参加者に紹介しました。
課題の共有や薬剤部の取り組みに対する理解に繋がったことがアンケートから伺えました。特に、薬に関する相談窓口が明確に示されたことに対して、院内外ともに良い反応が見られました。
それぞれの職種・立場の強みを生かし患者さんに寄り添う
講演では平成30年豪雨災害で被災した患者さんについて、急性期病院、クリニック、小規模多機能ホームそれぞれの立場から関わりを発表。「退院前訪問の大切さを改めて感じた」「生活者という視点でケア計画への追加・修正に繋いでいく必要があると感じた(看護師)」「それぞれの職種の強みを活かして連携できるように日ごろから取り組むことが大切」「在宅医療に関わることを考える契機になった」などそれぞれの立場で業務に生かせる気づきがあった回となりました。
進捗状況の共有で「連携のやりづらさ」をなくそう
高齢者支援センターからの情報提供として、退院日前日にサービス調整連絡を受け対応に追われ、その後ご本人から退院延期連絡があり、病院からは連絡がなかった…という事例が示されました。退院日決定前に進捗状況を伝えておいてほしいことや、医療との連携・時間がより必要なケースがあることを参加者で共有しました。
医療との連携、時間がより必要なケース
- ターミナル期
- 本人や家族が医療処置、医療機器の使い方の習得が必要
- 住宅改修や福祉用具など住宅環境の整備が必要
- 施設入所の希望がある
- 退院と同時にサービスが必要
- 介護保険未申請
- 新規のケース
- 虐待など家族関係に問題がある
- 生活困窮者など経済的な問題がある など
細かいコミュニケーションをとり、直接情報共有していくことが大切
緊急入院になりそうな様子で、在宅サービスの調整のため状況を問い合わせたが、個人情報守るために必要な情報が提供されない…という事例が示されました。医療提供者とケア提供者に有用な情報は異なるため、立場の違いで欲しい情報は異なります。不安なく支援していくためにはお互いに歩み寄ることが大切であり、聞き手側も工夫が必要。細かくコミュニケーションをとり、それぞれの知りたいことを情報共有することが大切。電話でのやり取りのみではなく、直接情報共有することが大切であるということを参加者で共有しました。