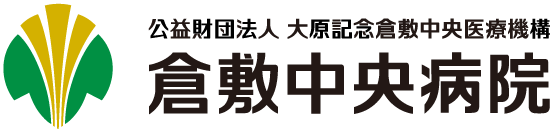主治医制からチーム制へ
 日本では伝統的に、主治医制を前提とした医療が行われてきました。医師は経験年数に応じて当然ながら能力に差があるため、若手医師が主治医となった場合、不安を感じる患者さんもいらっしゃるかもしれません。しかし、実際には経験の浅い医師を支える体制が整っていることが多く、その点についてはご安心いただきたいと思います。
日本では伝統的に、主治医制を前提とした医療が行われてきました。医師は経験年数に応じて当然ながら能力に差があるため、若手医師が主治医となった場合、不安を感じる患者さんもいらっしゃるかもしれません。しかし、実際には経験の浅い医師を支える体制が整っていることが多く、その点についてはご安心いただきたいと思います。
とはいえ、主治医は土日を含めて勤務することも少なくなく、その負担は決して小さくありません。
心臓血管外科では、重症かつ高齢の患者さんが多く、侵襲の高い手術を行うこともあるため、術前や術後の管理には医療チーム全体の総力が求められます。医療スタッフの経験値はさまざまで、時には個々の知識だけでは対応が難しい場面も発生します。だからこそ、多くのスタッフが関与し、お互いに不足を補い合うことで、より質の高い医療を提供できると考えています。また、各自が積極的に自分の役割を果たすことで、貴重な労力を無駄なく活用することが可能になるはずです。
当科では、2011年から主治医制に代わる新たな「チーム制」を試行してきました。医師全員が協力して患者さんの診療に臨むためには、患者さん一人ひとりの情報を共有できる環境が不可欠です。主治医が“患者に関するすべての情報”を把握していた従来の体制とは異なり、チーム医療では集合知を創出し、共通認識として形成するための仕組みづくりが必要でした。
以前は、1日に複数回カンファレンスを行うことで対応していましたが、患者さんの容態は常に変化します。そのため、従来の方法では、状況の変化に迅速に対応することが難しいという課題がありました。
そこで2018年に当院が導入したのが「Microsoft Teams」です。チーム医療には、患者さんの状態を医療スタッフがリアルタイムで議論できる環境が求められます。ただし、医師は多忙であり、心臓血管外科では1日平均で4件の手術があるため、どれだけ優れたツールがあっても、それが手術の合間に利用できるくらい、気軽に使えるものでなければ定着しません。
Microsoft Teamsは、少なくとも当チームでは、十数名のメンバー全員が日々の協議に活用しており、利用が定着しています。集合知を育てるうえで最も重要なのは「全員が意見を出す」ことです。これをリアルタイムで実現できるようになったことは、まさに一種の「コミュニケーション革命」とも言えるでしょう。
Teamsが広く活用されるようになった要因の一つには、個人用PCだけでなく、スマートフォンからも簡単にアクセスできるという利便性があります。何かしら相談を投稿すれば、必ず誰かが解決策を提示してくれる。この状態こそが、私たちが目指すチーム医療の理想の姿だと考えています。ただし、「情報の発信」は日頃から意識的に行わないと習慣化されません。そのため当チームでは、内容の重要度にかかわらず、何か起きた際には必ずチャネルへ投稿することを全メンバーに求めています。
このルールには、ナレッジの共有という目的もありますが、それ以上に「全員が意見を出す」文化を醸成するという意図があります。導入当初からこの点を繰り返し伝えてきたことで、現在では誰もが自然に Teams 上で活発な協議を行うようになりました。
(心臓血管外科主任部長 小宮達彦)
映像提供:日本マイクロソフト社