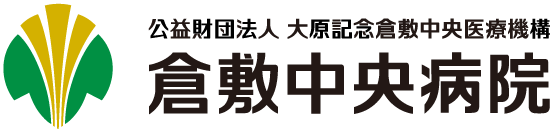臨床工学部
組織・実績
沿革

臨床工学部 部長
齋藤 真澄
医療系の各種の資格の中で臨床工学技士の歴史は比較的浅く、当院においても臨床工学技士の部門の整備が行われたのは比較的最近です。1984年に医療機器の中央化の検討が始まり翌1985年に医療機器管理センターが開設され翌1986年に医療機器課に名称変更し医療機器中央化が開始されました。1988年に法律が施行された臨床工学技士は、当院では医療機器課に配属され1991年には臨床工学技士5名で人工心肺業務への取り組みが開始されました。その後、透析業務、集中治療室での人工呼吸器をはじめとする医療機器や在宅人工呼吸などの管理も手がけるようになりました。
業務拡大に伴い生命維持に関連する医療機器とそれ以外の管理を分ける必要に迫られ、2001年に臨床工学技士20名余を擁するCEサービス室として医療機器課から分離・独立しました。夜間緊急の業務の増加に対応するため2004年の夜間拘束制の導入を経て2005年には他院に先駆けて当直制を導入しました。
生命維持に関連する医療機器の高度化、集中治療部門のみならず一般病棟での高度医療機器の普及に伴い急速に技士数は増加し、2008年に大掛かりな組織再編を行いました。
その後、2014年の組織改訂で、CEサービス室は臨床工学部と改称、手術センター支援室、集中治療支援室、人工透析センター支援室、医療機器管理室の4グループ編成となりました。
現在
現在では臨床工学技士数60名を有する日本有数の大所帯にまで発展しています。集中治療技術室、体外循環技術室、血液浄化技術室、医療機器管理室に分かれてそれぞれ専門性を発揮し、高度医療機器の管理を通じて第一線での診療のサポートを行っています。必要とされる診療支援を正確かつ迅速に行うことを第一とし、医師の指示の元で常に安全を最優先として業務にあたっています。
医療機器のトラブルの際には医療安全管理室とも連携をとりながら根本原因を把握し問題解決に努めています。医療機器の取り扱いについて他の医療スタッフへの研修にも積極的に取り組んでいます。
将来
高度で複雑な医療機器は医療の現場の隅々まで普及しつつあり、その取り扱いには細心の注意を要しますが、機器の進化は日進月歩で多くの医療スタッフはそれに追い付いていけません。日常の診療の中で臨床工学技士が必要とされる場面は数多く、今後ますます業務を拡大していく必要があります。さまざまな業務をこなすためには、専門性に加えて汎用性の高い医療機器に関して全般的に取り扱えるようになる柔軟性を備えた技士が求められています。ほぼすべての診療科を網羅する大規模急性期病院の特質を生かしてさまざまな現場を経験できるよう技士の養成にも力を注いでいきます。
臨床工学部の組織
臨床工学部は4つの室に分かれており、それぞれが専門性を生かした業務を行っています。
現在60名(2019年4月末現在)が在籍しており、各室の人数配置は以下の通りです。
各室の詳細は 業務紹介のページをご覧ください。
- 部長:齋藤 真澄
- 副部長:金谷 浩行
| 臨床工学部各室 | 室員数 |
|---|---|
| 集中治療技術室 | 21名 |
| 体外循環技術室 | 7名 |
| 血液浄化技術室 | 16名 |
| 医療機器管理室 | 16名 |
当院組織内での位置づけ
| 年 | 事項 |
|---|---|
| 1984年 | 医療機器中央化検討委員会発足(事務長、看護師長、工務など) |
| 1985年 | 医療機器中央化開始 事務部門 医療機器課 開設 |
| 1988年 | 臨床工学技士法 臨床工学技士誕生 |
| 1991年 | 人工心肺業務強化 臨床工学技士養成校新卒者初採用 |
| 1993年 | 人工透析業務強化 |
| 1994年 | ICU・CCU業務強化 |
| 1995年 | 在宅人工呼吸器業務強化 |
| 2001年 | 診療支援部門 CEサービス室 発足 (医療機器課と別組織に) ICU・NCU業務強化 |
| 2003年 | 心カテ室業務 SAS関連業務 開始 |
| 2005年 | 新9棟開設 夜間緊急業務⇒当直体制移行 NICU・9棟CCU 業務強化 夜間緊急業務⇒当直体制移行 |
| 2009年 | CE組織を業務で4グループに分割 |
| 2010年 | 新3棟開設 夜間緊急業務⇒交替制移行 |
| 2014年 | 医療技術部門 臨床工学部 発足 4グループの名称を変更 |